爆速で進むライム新規事業に、大企業50代は通用するのか?—異色のタッグが生んだ想定外の化学反応

「自分が業務で培ってきた経験を活かして、幸福な地域社会の実現をサポートし、日本を元気にしたい」。長年、大企業でキャリアを積んできた田中勇司さんは、そんな想いを胸に新たな挑戦の扉を叩きました。きっかけは、仲間達が、宮城県気仙沼市の復興支援や静岡県南伊豆町での町おこしなど、地域活性化の取り組みに活き活きと取り組んでいたこと。生まれも育ちも関東圏で「地域」とは距離があった田中さんは、徐々に「もっと地域を元気にすることに貢献したい」という気持ちを強くしていきました。
一方、神戸を拠点に「事業づくりを、誰もができることにする」というミッションを掲げ、事業立上げを支援する、株式会社アドリブワークス。COOである栗山依子さんが日々走りながら事業化に奔走していたのは、日本でも珍しい国産ライムの事業化でした。
大きな企業の中で、多様な経験を積んできたベテランと、トライ&エラーを繰り返しながら爆速で突き進むベンチャー カルチャー。一見すると、その文化や働き方は相容れないものに思えます。しかし、この異色のタッグは、オンラインでの2ヶ月のインターンシップを終えて、共に事業を創るパートナーとして歩み出す、という関係に辿り着きました。
本記事では、田中さんとアドリブワークス栗山さんの出会いから、インターンシップでの協働の軌跡を紹介します。キャリアの岐路に立ち、「自分の経験は、この会社の外で本当に通用するのだろうか?」と自問するすべてのビジネスパーソンに、新たな可能性の扉を開くヒントをお届けします。
「ちゃんとやりたい、が強すぎて遅い」—大企業人材に抱いていた不安
「正直に言うと、最初は不安がありました。」アドリブワークスCOOの栗山さんは、インターンシップ開始前をそう振り返る。外部との協働や人材の活用に積極的な風土がある一方、企業文化や言語が違う方とゼロイチを作っていくことに独特の難しさを感じている、という。
「まだ具体的になっていないことをキャッチアップして整理、言語化するスピード感はあるものの、『ちゃんとやろう』という意識が強すぎることと、やってきていないことへの不安が前に出て、実行フェーズになると踏み込めない人たちも見てきました。私自身もベンチャーの世界に入った当時はそうでした。」
朝令暮改も厭わない、スピード感が生命線の新規事業開発にとって、完璧さを求めるあまり実行が遅れる仕事の進め方は、時に事業の成長を阻害する足枷となりかねない。田中さんとの最初の面談も、「外から見た私たちを客観的に教えてもらえるといいか」くらいの気持ちで参加したという。オンラインでの初対面だったが、画面越しでも田中さんの受け答えや姿勢から、人となりは十分に伝わってきた。
決め手は、田中さんの「人柄」。面談時の田中さんから「誠実そう」「自分ごと化して、変化のスピードにも柔軟に接してくれそう」との実直な印象を受け、抱いていた「大企業のメーカーさん」というイメージとは、ちょっと違うかもしれない、と思えた、という。
「52週計画」から「ライム沼」へ—田中さんの提案に”全乗っかり”で進む
インターンの当初のゴールは明確だった。アドリブワークスが手掛ける「国産ライム事業」のマーケティング戦略として、「52週計画」を策定すること。年間を通じた販売・販促計画を体系的に描き出すという、まさにこれまで食品メーカーの営業部門で、小売業向けの提案サポートに携わってきた田中さんの知見が活きるテーマだった。
田中さんの動きも明解だった。まず取組みの全体像と各会議の議題を整理して合意した後に、毎週の定例会議前に資料を準備。会議の目的とゴールを明確化した。具体的な提案内容だけでなく、議事録を用意し、進捗はPowerPoint資料に纏めて共有。栗山さんが「田中さんの提案に全乗っかりしよう」と思えるものであり、日々時間に追われる中で、「本当に有難かった」と振り返る。
全てオンラインでの定例会議だったが、事前に資料が共有されることで、限られた時間でも密度の高い議論が可能になっていた。「頭の中で考えて決めて、すぐ実行に移してしまうので、思考のプロセスが可視化されにくいんです。田中さんが毎回資料にまとめてくれることで、自分を実感できただけでなく、社内のメンバーへの共有も出来て、非常に助かりました。」

田中さんのライムラバーっぷりを示す自宅での料理の品々
AIの壁打ちではない、田中さんだからこそ出来た「心のセーフティネット」
田中さんとの協働がアドリブワークスにもたらしたものは、具体的な計画書や資料だけではなかった。栗山さんは、その本質的な価値を「スキル以上のもの」だったと語る。
普段、経営者の一人として連続する意思決定と、その責任を負う立場にある栗山さんにとって、田中さんは客観的かつ俯瞰的な視点を持つ貴重な相談相手となった。「安心して喋れる、心のセーフティネット」のような存在だった、と言う。物理的には離れた場所にいながらも、週に一度、画面越しに顔を合わせる時間が、日常のカオスから一歩引いて思考を整理する“場”として機能していた。
奇しくもアドリブワークスは、頭の中のアイデアを深掘りして可視化し事業計画策定を支援するAIサービスも手掛けている。日常的にAIを壁打ちとして使っている栗山さんだからこそ、感じた田中さんとの協働価値と言えるかもしれない。「AIは優秀な営業のように、もっともらしい答えを返してくれ、それはそれで議論のしがいがありますが、多様な経験をした生きている人が感じたことや、ネットには上がっていない情報だからこそ議論が深まる価値がある」。
田中さんとの壁打ちを通して、当初の「52週計画」を越えて、インターンは予期せぬ方向へと進化を遂げていく。きっかけは「このライムを使って何か新しい商品を作ってみたい」という声が顧客から上がり始めたこと。田中さんと顧客の反応を話す中で、「ライムラバーのファンコミュニティビジネス」という、想定外の構想へと発展していった。
インターンから共創パートナーへ—「ライムマスター」と描く未来
2ヶ月間のインターンを終え、共にライム事業を創るパートナーとして関係を継続している田中さんと栗山さん。インターンを振り返って、栗山さんに、田中さんについて聞いてみた。「状況が変わったり、新しい情報が出てきたりした時に、田中さんは変化を嫌がらず、非常に柔軟に切り替えて考えてくれました。」
さらに、田中さんが自ら「ライム沼にはまった」と語るほど、ライムを楽しみ、「自分ごと」になったと感じたことも大きかったという。「田中さんには、受発注の関係ではなく、これから創っていくライムのファンコミュニティの『ライムマスター』として君臨してもらいたいんです」。
インターンシップ終了後のアンケートで、栗山さんは田中さんへこうメッセージを送っている。 「面白いことを一緒に企てていきましょう!」
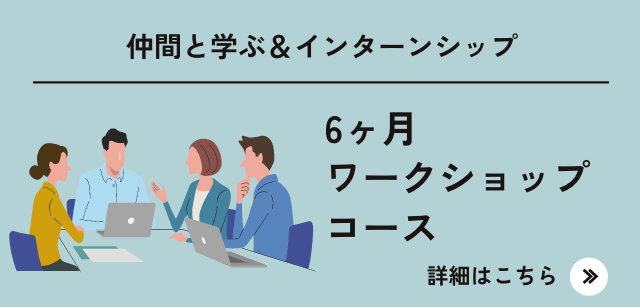
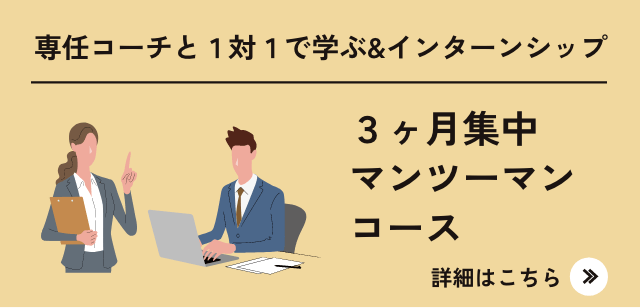
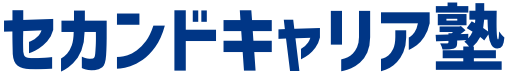

 50代からの大人のインターンシップ事例をお届け!
50代からの大人のインターンシップ事例をお届け!